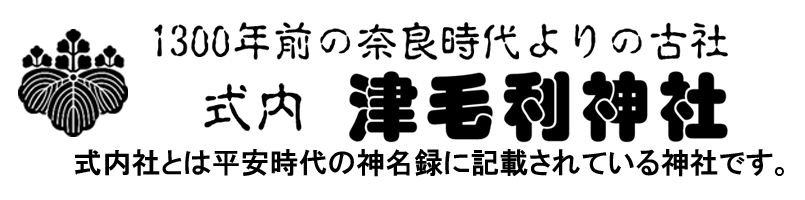王の舞面
昭和56.3.16 静岡県指定/有形文化財 彫刻
舞楽は普通「左方の舞」と「右方の舞」とを組みあわせて一番として舞う。仮面は貴徳の面と伝承され右方の舞に属し、左方の舞の散手と対になって舞われる。
また、この面は偉丈夫の相を示し、朱塗の鼻高く厳しい表情で、掘り方は力強く鎌倉時代の名のある中央仏師の作と推定される優れた面である。
現状は形の崩れもなく、また、漆のはがれも少なく、ほぼ完全な形で保存されており地方に伝わることは数少ない貴重な面である。
「永福寺を鎌倉御家人」資料解説より
神奈川県立歴史博物館
本面は高い鼻を持ち眉根を寄せて目をいからせ口をへの字に結ぶ、津毛利神社では昭和初期頃まで祭礼の露祓いの「王の舞面」として使用され鼻高面の一種として伝来した。
鼻の先を含んで面全体を一本で掘出し表面には布張りをして漆で固めて彩色を施す。右耳周辺に虫食いの痕が残るが、後補の部分は少なくない。一方で赤色に彩色されることから舞楽面の散手の可能性がある。
額や口元のしわやへの字の口の結び方、耳をあらわす点など鶴岡八幡宮の散手と共通する部分が多いこともこの二面の近似性がうかがえる。
舞楽の散手は左方舞で鉾をもった武人が赤系統の装束を身に着け勇敢に舞う演目である。緑系統の装束を着ける右方舞の貴徳の前に演じられることが多い。
散手とすれば東海道筋に伝わる舞楽面として貴重な存在で、愛知・熱田神宮の舞楽面群、静岡・鉄舟寺(久能山伝来)の蘭陵王面、鶴岡八幡宮の舞楽面群が知られるが、それらに匹敵する古面とて注目されよう。